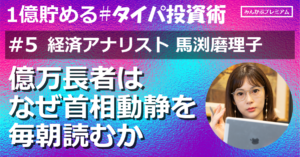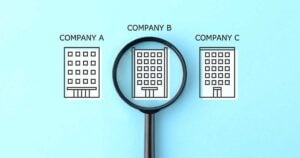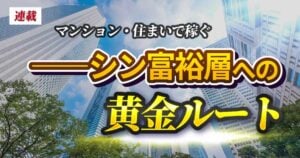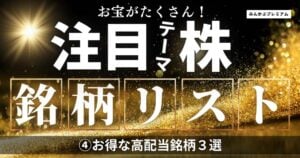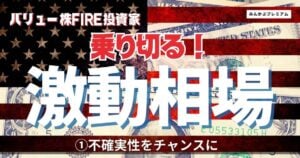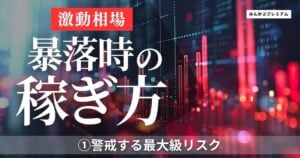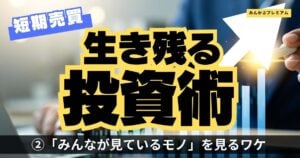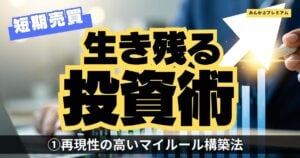「健康経営銘柄」の不都合な真実…「半数はROE8%未満」の激アマ査定の実態

従来、従業員の健康管理は企業にとって単なるコストや「自己責任」と考えられてきたが、昨今では経営リスクの回避、業績向上のための取り組みとして概念化されている。それが今、注目されている「健康経営」である。その導入実態と課題について、気鋭の経済アナリスト・馬渕磨理子氏に聞いた。
健康経営をしているかどうかを海外の投資家も注目
健康経営はアメリカの経営心理学者ロバート・ローゼン博士が1990年代に提唱した理念。
1992年にアメリカで出版された「The Healthy Company」で、「健康な従業員こそが収益性の高い会社をつくる」という思想を提唱したことが始まりとされています。
ただ、日本で株価にいい影響が出ているかというと、現状では何とも言えません。
実際に、健康経営が企業の収益性(ROE、ROA)に影響していなかったという研究結果もあります(https://www.jc.u-aizu.ac.jp/news/management/gr/2020/08.pdf)。
とは言え、我が国でも健康経営の推進には力を入れており、経済産業省は健康経営銘柄として50社を選定しています。
2022健康経営銘柄(https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220309001/20220309001.html)