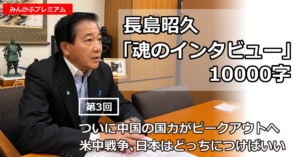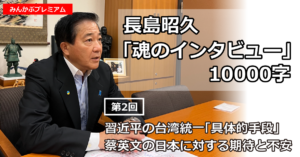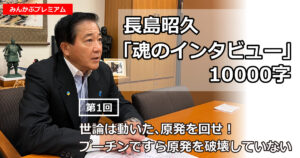「3泊5日・67万円」で大炎上!港区立中学校「シンガポール修学旅行」…子供7人に1人が”貧困状態”の日本が掲げる教育の機会平等・格差是正のお笑い

タワマンが林立し、ハイスペックな人物も多い東京都港区。少し前にはセレブな男性たちとパーティーを楽しむ「港区女子」なる言葉も流行ったが、その華やかなイメージは子供たちにも向けられる。
港区は区立中学3年生の修学旅行先を海外にすると発表し、国内実施時との差額分は区が負担してくれるというのだ。
経済アナリストの佐藤健太氏は「かつては都内の公立小学校が高級ブランド監修の標準服を採用して話題を集めたが、『港区チルドレン』の海外訪問にも賛否の声が上がっている。他地域で暮らす子供たちとの新たな格差を感じさせることになりそうだ」と指摘する。
全ての区立中で海外修学旅行を実施し、国際人を育成するという
「港区は国際性豊かな地域で、およそ人口の7%、2万人近い外国籍の方が暮らしている。国籍も約130に及ぶ。港区は従前から国際人育成に力を入れてきた。これまでの取り組みの集大成として全ての区立中学校で海外修学旅行を実施する」。港区の武井雅昭区長は9月1日の記者会見で、来年度にシンガポールで修学旅行を行うことを明らかにした。