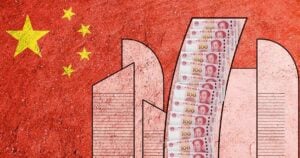ひろゆきはなぜ再ブレイクできたのか…リハック高橋Pの選定基準「マスメディアが誤った情報を発信する責任は重い」「既得権益を持たない人に注目している」

最近、連日のようにXのトレンドに入っているのが、動画メディア「ReHacQ(リハック)」だ。ReHacQの報道が、東京都知事選や兵庫県知事選など、最近行われた選挙において、有権者の投票行動に大きな影響を与えているのはほぼ間違いないだろう。
ReHacQが目指すものについて、プロデューサーの高橋弘樹氏に直撃したーー。みんかぶプレミアム特集「オールドメディア vs SNS」第5回。
目次
ReHacQ高橋Pの人選基準は「少し気になる人」かどうか
ーー今回の兵庫県知事選を通じて、ReHacQが世論を動かす力を持っていることが印象的でした。高橋さんは出演者をどのような視点で選んでいるのでしょうか?
出演者の人選についてですが、抽象的な表現にはなりますが、「少し気になる人」に焦点を当てています。特に、物事の見方が一般の人とは異なる方には強く惹かれます。
例えば、成田悠輔さんや石丸伸二さん、斎藤元彦さんなどは、まだ世間に広く知られていない段階から注目していました。
成田さんに関しては、初めてお会いしたときから独特の雰囲気を持っていました。具体的には、マントを着ていたり、話し方に個性的な角度があったりと、非常にユニークな印象を受けました。また、議論の進め方も独特で、相手の発言をそのまま受け取るのではなく、俯瞰的な視点や真逆の視点から考察しているように感じました。そのような姿勢に触れて、「この人は面白い」と興味を持つようになりました。
何度も出演される方については、「面白いと思える何かがあるかどうか」が重要なポイントになります。それが継続出演につながる場合もありますし、成田さんのように、結果的にメディアで大きな影響力を持つようになるケースもあります。ただし、特定の人物を「推す」という意識はあまり持っていません。
ひろゆきはなぜ再ブレイクしたのか
ーーひろゆきさんもReHacQを通じて再ブレイクしたように感じますが、その点についてはどのようにお考えですか?
ひろゆきさんは、もともとニコニコ動画などで有名でしたが、私が出演をお願いした2020年頃は再び注目を集めるようになっていました。彼については賛否両論ありますが、やはりその発想の面白さが際立っています。
例えば、動画の切り抜きを許可し、自身を「フリー素材化」するという新しいビジネスモデルを構築した点は、非常に斬新だと思います。
また、彼の強みの一つは、専門家ではない立場から社会問題について語れることです。専門家ではないにもかかわらず、独自の視点で課題を浮き彫りにする力を持っています。さらに、「嘘は許さない」という姿勢や、「論理的に破綻していないか」といったエンジニア的な視点を持っている点も魅力的です。こうした特徴が、メディアにおいて彼が重宝される理由の一つだと思います。
「既得権益を持たない人」がキーワード
また、ReHacQのMCに関しては「既得権益を持たない人」というのは重要なキーワードの一つです。そのため、そうした立場の人の言葉に注目する姿勢は一貫しています。
ーーなぜReHacQでは「既得権益を持たない人」に注目するのでしょうか?
極端に言えば、自由な発言ができることが理由ですね。例えば、ひろゆきさんは海外在住で国内のしがらみを持たず、石丸さんも会社を辞めて裸一貫で政治に挑まれた方で、いまは無職です。このような方々は特定の組織やしがらみに左右されることがなく、自由な発言が可能です。その自由さが新しい視点を生むきっかけになるため、しがらみのない人が言論空間の中に何人かいることは非常に重要だと考えています。
ただし、しがらみがないことだけでは十分とは言えません。自由である一方で、発言が無責任になったり、誹謗中傷に走ったりしないという点も大切です。そのようなバランス感覚を持つ方こそが、最終的に多くの支持を得られるのだと思います。
なぜReHacQはあえて儲からない旅番組をやっているのか
ーーReHacQは旅番組が多い印象を受けますが、それにはどのような意図があるのでしょうか?また、旅番組はマネタイズが難しい側面もあると思いますが、その点についてお聞かせください。
基本的には、「堅苦しい番組よりも楽しい番組を作りたい」という思いがあります。「ReHacQ旅」は地方創生や市民との対話をテーマにしており、訪問先もXで募集して決めることが多いです。これまでにも、ひろゆきさんや石丸さんが地方の街に出向き、現地の人々と交流したり、観光地っぽくない場所を訪れ、その土地の魅力を発掘したりしてきました。
実際に現地に足を運び、自分の目で確かめることはとても大切だと思います。そうすることで、その地域の課題や、まだ知られていない素晴らしい魅力を発見することができます。一応、地方創生を「プチミッション」として掲げているので、そうした視点で取り組んでいます。
マネタイズについては、旅番組は基本的に赤字で、コストパフォーマンスも良いとは言えません。ただし、メディア運営を個々のコンテンツの収支だけで判断すべきではないと考えています。
なぜなら、東京で国政について語ったり、大企業の経営者にインタビューするだけが政治や経済メディアの役割ではないと思っているからです。「ReHacQ旅」では、地元の中小企業が応募してくることも多く、地場産業の経営者の話を聞く機会があります。また、その中にはひろゆきさんや石丸さんと語り合いたいと考える方もいて、そうした交流を通じて得られる肌感覚が、政治や経済の大きな側面を理解する上で重要だと感じています。
実際に富山を訪問した際には、北陸地方における自民党支持層の空気感や、産業構造を実感しました。このように、旅番組を通じて得られる体験は、単なる対談番組では得られないリアルな視点を提供してくれると考えています。
メディアとして強くなる過程が重要
ーーReHacQはYouTubeなどで動画を無料配信していますが、収益性はあるのでしょうか?
正直なところ、コストもかかりますし、すぐにめちゃくちゃ儲かるものではありません。ただ、メディアにおいては、一時的に収益を上げることよりも、「メディアとして強くなる過程」が重要だと考えています。もちろん、黒字を維持することも大切ですが、それはあくまで世の中に発信したいコンテンツを届けるための手段であり、目的そのものではないと捉えています。
ReHacQは黒字ではありますが、それは持続可能な形でコンテンツを発信し続けるための最低条件だと考えています。
会社全体で見ると、映像制作の部署もあり、いくつかの柱を立てながら運営しているといった形です。
マスメディアが誤った情報を発信する責任は重い
ーー今回の兵庫県知事選では、リベラル色の強いマスメディアの報道よりも、SNSの影響力が強かったという印象を受けました。今後、報道の在り方はどのように変わっていくとお考えですか?
マスメディアもSNSもそれぞれ危険な側面がありますが、現行法での対応が基本だと考えています。例えば、SNSでの誹謗中傷やフェイクニュースなどは名誉毀損や、風説の流布として取り締まるべきだと思います。一方で、マスメディアについては、今回の県知事選において選挙前の報道のあり方に異議を唱える声が多かったことが、民意が傾いた一因とも言えると思います。
民主主義やメディアのあり方について「これが最も良い」という答えを出すのは難しいですが、国民はより害が少なく、欠陥のない方を選ぶのが現実的だと思います。その意味では、電波や紙媒体といった大きな影響力を持つマスメディアが誤った情報を発信した場合、その責任はSNS以上に重いと言えます。そのため、マスメディアにはより厳しいルールとペナルティが課されるべきですし、自浄作用が求められると考えます。電波を優遇された価格で使用している現状や、軽減税率を適用されているといった優遇にはそれ相応の責任が伴うべきです。
SNSに関しては規制を強化すべきだという議論が出ることがありますが、一方で、自分たちの報道に対する疑義と実質的な責任が少ないマスメディアの姿勢には疑問を感じます。
言い訳に終始してしまう今のマスコミは問題
ーー公平性を担保するために、マスメディア側にはどのような改善が必要だと思いますか?
今回の県知事選に関して、「公職選挙法や放送法を理由に選挙期間中の公平な報道ができなかった」というマスメディアの言い分がありました。しかし、実際にはこれらの法律は、公正である限り討論や報道を認めています。それを「やらなかった」というだけなのに、「我々は放送法や公職選挙法との兼ね合いでできなかった…」という姿勢は問題だと感じます。このように、マスメディアが自分たちの報道姿勢について言及しない点は、気持ちが悪いなと思います。
全体として表現の自由は確保されるべきだと考えますが、それを盾にした誤報や偏向に対しては今までなすすべがありませんでした。しかしいまはWebにも色々なメディアが存在します。今回の選挙結果は、国民がこうした問題に疑問を抱いたことの表れではないでしょうか。
マスメディアもSNSも、社会への影響をしっかり意識しながら、柔軟に修正していける。そんな社会が望ましいと思いますし、それこそが今後のメディアとしての信頼性を維持する鍵になると考えています。
ReHacQは「堅苦しくない」スタイルで何を目指すのか
ーーReHacQはライブ配信も人気ですが、堅苦しくないスタイルは意図的なものなのでしょうか?
そうですね。本音を引き出すにはリラックスした雰囲気が大切です。ライブ配信では、飲み物を片手に雑談形式で進めることもありますが、それも自然な形で対話を深めるための工夫です。
ReHacQの最大の目的は、権力の監視や不正の暴露ではありません。2つの意識に基づいています。1つ目は、批判の対象になりがちな人や組織の、「魅力」もしっかり引き出すこと。もう1つは、発言や行動が事実に基づいているか、論理的に矛盾していないか、その方のリアルな姿と思考を映し出すことです。その一次情報を視聴者に届け、その評価を委ねるスタイルを目指しています。砕けた雰囲気の配信スタイルも、リラックスした対話の中で本音を引き出すための工夫の一つです。
ーー最後にReHacQの今後の展望について教えてください。
ReHacQは政治的な側面で注目されることが多いですが、実際には経済に関する情報も豊富に提供しています。政治に興味を持っている人の何割かが経済にも関心を持つようになったり、その逆に経済に興味のある人が政治に関心を広げたりする。そうした異なる興味を持つ人々がReHacQに集まり、隣接分野への関心が広がっていくことが、理想的なメディアの形だと考えています。そのような存在になれたら良いなと思っています。