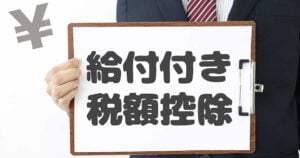「投資家向け広報」に優秀人材を投入する時代に…日本企業に迫る「協働エンゲージメント」の波

機関投資家が連携し、企業と持続的企業価値向上を目指した対話を行う「協働エンゲージメント」の潮流が日本にも訪れている。長らく株式市場と一定の距離を保ってきた日本企業だが、企業統治改革や国際的な動きに押され、株主との対話の重要性が高まっている中では必然なのかもしれないが、果たして「協働エンゲージメント」は今後どのような影響をもたらしていくのか。日経新聞の編集委員である小平龍四郎氏が解説していく──。
目次
「協働エンゲージメント」が日本企業に迫る変革
日本の企業統治(コーポレートガバナンス)改革が始まって約10年。株式市場と疎遠だった日本企業もようやく株主との対話を始めた。ガバナンス改革の推進力のひとつだった「スチュワードシップ・コード」(SCC)は3度目の改訂で、複数の機関投資家が連携して企業に働きかけをする「協働エンゲージメント」を促進する姿勢を持った。日本企業は株主との対話に一段の緊張感をもって臨まなくてはならなくなる。
「協働エンゲージメント」とは米国や英国では一般的に見られる手法で、同じ企業に投資する2社以上の資産運用会社などが共通のテーマを実現するために用いる。1社ずつ別々に働きかけをするより、企業分析に費やす人やお金の面でのコストを有効に使える。浮いた時間や人員を別の企業への働きかけに割くこともできるので、全体として企業と株主の対話は質量ともに増す。
協働エンゲージメント(Collective Engagement)が強く意識され始めたのは、2012年の英国だ。この年、経済学者のジョン・ケイ氏が英国の株式市場の問題点を総括する「ケイ・レビュー」を発表。このなかで、英株式市場には単独で大きな力を企業にふるう大株主は存在せず、所有構造がきわめて分散していることを指摘した。所有の分散は民主的ではあるものの、株主の影響力も分散してしまうことから、経営に対する資本の規律付けが弱くなっているという問題も生じていた。
そこで、ケイ氏は機関投資家が力をあわせて企業を監督し、様々な要求をするための組織をつくるよう提言した。ケイ・レビューの提言に沿ってインベスター・フォーラムができたのは2014年。2014年の活動報告書によれば、資産運用会社や年金基金など51社が加盟し、昨年はハーグリーブス・ランズダウン、ヒプノシス・ソング・ファンド、ヴィストリー・グループの3社に協働エンゲージメントを実施している。