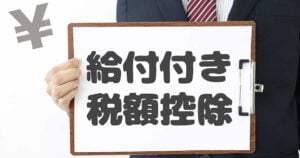成田悠輔「個人によって物の値段が異なる社会がやってくる」そして誰もが比較されない社会へ

あるものが100円で販売されていて、所得の多寡にかかわらず、誰しも100円を出して購入する。私たちが「当たり前だ」と思っているこのような取引のあり方に、経済学の成田悠輔氏は「違う物理法則で生きる違う星の生物を、同じルールでスポーツさせて競わせてるようなものではないか」と疑義を呈する。今後起こりうる価格システムの変化について、成田氏が考える。全3回中の3回目。
※本稿は成田悠輔著「22世紀の資本主義 やがてお金は絶滅する」(文藝春秋)から抜粋、再構成したものです。
第1回:成田悠輔「わからなさこそが資本主義」なぜ金より株が上昇したのか
第2回:なぜ人はブランドバッグをありがたがるのか…成田悠輔「人は現実よりも幻想を評価する」
目次
「誰が買っても同じ値段」システムは衰退する
滅亡まで極端でなくても、衰退は運命である。一次元化され匿名化されたお金、いま私たちが何の疑いもなく受け入れているお金が支える「一物一価的な全員共通価格システム」の衰退だ。どういうことだろうか。
物やサービスに値段がついていて、その分だけお金を払えば誰でも買える。つまり値段は全員共通で誰が支払うかを問わない。こういう仕組みに私たちは慣れ親しんでいる。そんな一物一価的な全員共通価格システムが支配的なのは、またしても記録・データが貧弱だったからだろう。それぞれの人ごとに属性や履歴をたどってその物やサービスを手に入れるに値する人かどうか、いくらで取引するのがいいかを決めることが、これまではデータ的にも通信・計算環境的にも難しかった。
売り手と買い手が出会うたびにいちいち価格交渉するのも面倒すぎる。だから全員共通価格システムを使えば、適切な買い手の選別を粗く雑に代行してくれる。特に単価が小さいものについては。一人一人にとってちょうどいい価格を計算したり交渉したりする手間も省いてくれる。価格の分だけお金を持っていればどんな嫌われ者でも前科者でも買える、単純明快で透明な仕組みだ。
経済の記録が実態に追いつくにつれ、しかし、データの制約は緩んでいく。一人一人のデータ履歴を追って、その人が何者か、取引していいか、いくらくらいの値段をつけるのがよさそうか調べ決めやすくなっていく。通信や経済の制約も緩んでいる。一物一価的な全員共通価格システムを使わなければならない必然性が緩んでいくことになる。
これまでも、交渉や一人一人にバラバラに配られたポイントやクーポンによって価格が人によって違うという状況はそこそこあった。それが全面化し、自動化し、あらゆる場所で不眠不休で起きる。お金で測られた全員共通価格に投影されてこなかった様々な履歴情報が声を上げはじめる。
実際、今の一物一価のお金・価格や税金の仕組みは奇妙である。十席しかしない小料理屋も、数千万人が自室で遊ぶスマホゲームも、同じお金で比べられて同じ税制があてはめられる。違う物理法則で生きる違う星の生物を同じルールでスポーツさせて競わせてるようなものではないだろうか?
こんな不思議なことになっているのもまた、事業や企業を売上とか従業員数とか雑すぎるデータでしか捉えられない粗さのせいである。より豊かな属性や履歴に基づく一物多価経済は、より細かな区別によって価格も税金もそれぞれの個人や企業ごとにより繊細にバラバラにできる。