羽生結弦の“勇気”の話をしよう。絶望と死神ばかりの世界…興行の世界で希望に手を伸ばす“勇気”の話を。『羽生結弦をめぐるプロポ』「勇気」(3)
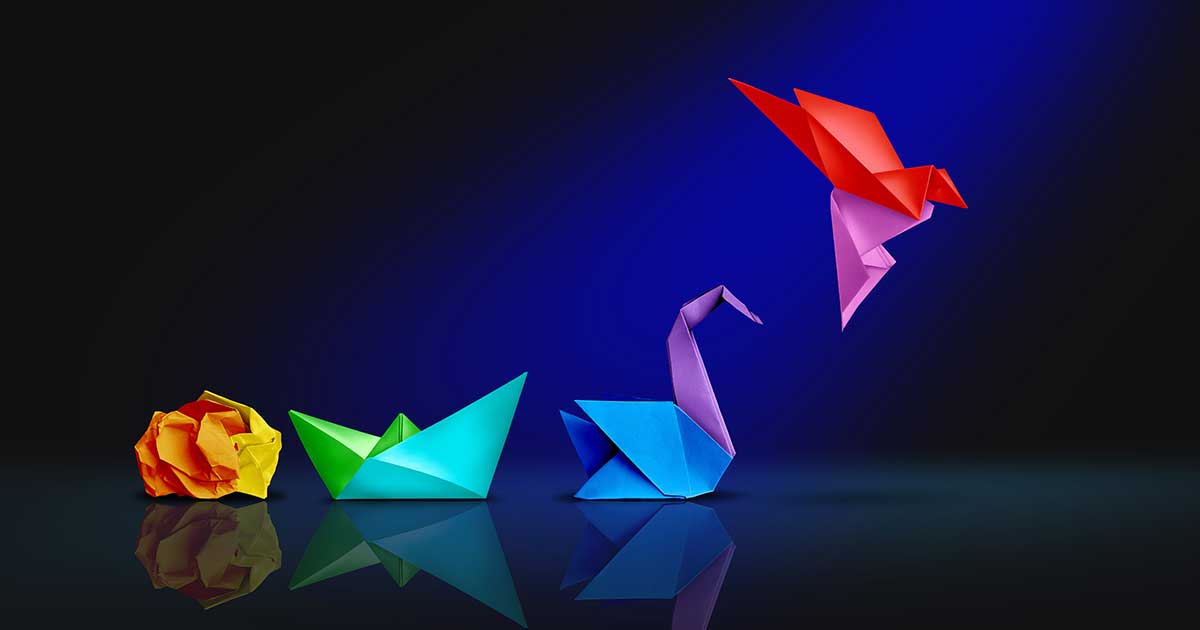
目次
興行というプレッシャー
興行とは、まさに水物――。安易な人が安易に思うよりお金を払って人に来ていただく、それも生活におおよそ関係のない娯楽で来てもらうというのは本当に大変なのだ。
人間である限り何があるかなんてわからない身一つの仕事、羽生結弦という存在あっての仕事。病気になったり、あるいは事故や怪我、どうにもならない天災に遭ったりするかもしれない。
プロアスリート宣言後もこのプレッシャーを率直に羽生結弦は語っているが、まさしく競技会とは別の興行というプレッシャーたるや想像に余りある。いくらでも平易な道はあるはずなのに。
なぜ危険な興行に打って出るのか
――思えば、客演でも十分だろう。これも客演を軽んじているのでない。客演で呼ばれることもまた、その人の勇気の積み重ねの結果である。それが羽生結弦なら引く手あまたであることは言うまでもない。危険な興行に打って出なくても羽生結弦は十分に「食べていける」はずということだ。
それでも羽生結弦は自分のやりたいことのために、多くの人々のためにも自身の公演が、興行が必要だった。
私の常々引く思想家アランは「行動すること」としてこう記している。※1
「あの競技ランナーたちはみんな、おおいに刻苦する。あのサッカー選手たちはみんな、おおいに刻苦する。人間は快楽を求めるものだと、どの本にも書いてあるが、そうとはかぎらない。むしろ人間は刻苦を求めている」
「人間は自分からやりたいのだ。外からの力でされるのは欲しない。自分からあんなに刻苦する人たちも、強いられた仕事はおそらく好まない」
羽生結弦の興行もまた刻苦には違いない
「だれだって強いられた仕事は好きではない。だれだって身にふりかかる不幸はいやだ。止むを得ないと感じてよろこぶ者はいない。しかし、自分の意志で刻苦をつくり出すやいなや、ぼくは満足する」
















