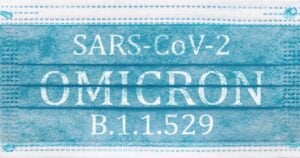第1回 熱海土石流災害[その1]頻発する集中豪雨、「万が一」に備えて行政支援をマークせよ!

本連載は、ニュースで報道される事件・事故などをファイナンシャルプランナーが調査して、「損害額はどれくらいか」「行政の支援はあるのか」「損害に備えるための手段は何か」といった情報を、皆さんにお伝えいたします。
第1回は、令和3年7月に起きた熱海土石流災害を取り上げます。
今年は大雨による被害が多く発生し「近くの川が氾濫したらどうしよう」「がけ崩れが起きたらどうしよう」と思った人も多いのではないでしょうか。
本記事でお伝えする被害状況、災害支援の実態、土砂災害を保障する損害保険などの情報は、皆さんがこうした災害に遭われた際に必ず役立つものです。
「災害対策をしていない」「災害対策が十分か不安だ」という人はぜひご一読されて、今後の対策にお役立てください。
目次
熱海土石流災害の概要
令和3年7月3日、静岡県熱海市伊豆山地区で大規模な土砂災害が発生しました。
気象庁によると、このとき静岡県の複数の地点で72時間降水量が観測史上1位を更新するなど、静岡県から南関東にかけて記録的な大雨となりました。