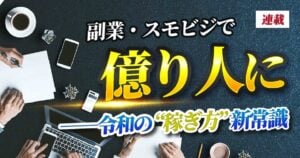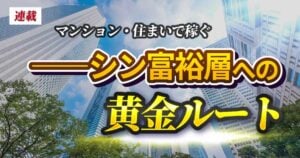人々が餓死する国に…1ドル200円時代! 「年金が大ピンチ」中小企業は”退職金あっても暮らすの困難”

日本人の老後を支える年金。受給開始年齢は当初の55歳から段階的に引き上げられ、現在は65歳まで上昇した。少子高齢化が進む中で受給金額の増加は望めず、負担ばかりが重くなることが予測される年金に対して、日本人、とくに若者はどのように向き合うべきなのか。プレミアム特集「株投資完全ガイド」の第3回は、経営コンサルタントの小宮一慶氏に話を聞いた――。
目次
政府が示す標準的な年金モデルで本当に暮らしていけない
現在、政府は標準的な年金モデルとして「会社員の夫と専業主婦の妻の世帯で月額24万円弱を支給する」と想定しています。この金額で夫婦二人、死ぬまでゆとりを持って暮らすことができると思いますか。
結論から言えば、暮らせる人もいれば暮らせない人もいます。10年前に亡くなった私の母の話をしましょう。父が亡くなってから、母は17年間ほど公務員だった父の遺族年金で過ごしました。その額は17万円ほど。決して多いとは言えませんが、大阪郊外にある小さな家で花や野菜を育てながら、悠々自適の生活を送っていました。
私に対しては、よく「あんたよりずっと心豊かでいい暮らしをしている」と自慢していたものです。遺族年金から貯金までしていました。
母の場合、自宅を持っていたことも大きいですが、それでも中にはひとりで暮らしていた場合でも「17万円では足りない」という人もいるでしょう。将来に不安を感じたときにはまず、自分の暮らしに必要な支出と老後に入ってくる収入を計算することが重要です。
一般的には、65歳以上の夫婦二人がゆとりある生活を送るためには、36万円程度が必要だと言われています。政府による標準的な年金モデルとの乖離(かいり)を月13万円として計算すると、年間156万円のマイナスです。これが20年間続くとなると3120万円。少し節約して月10万円の乖離に抑えても2400万円が必要になります。