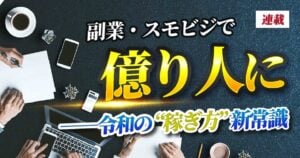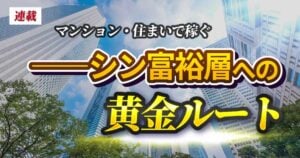恐怖のドル円150円にインフレ地獄…逆風に打ち勝つ「米国積立投資、8つの鉄則」
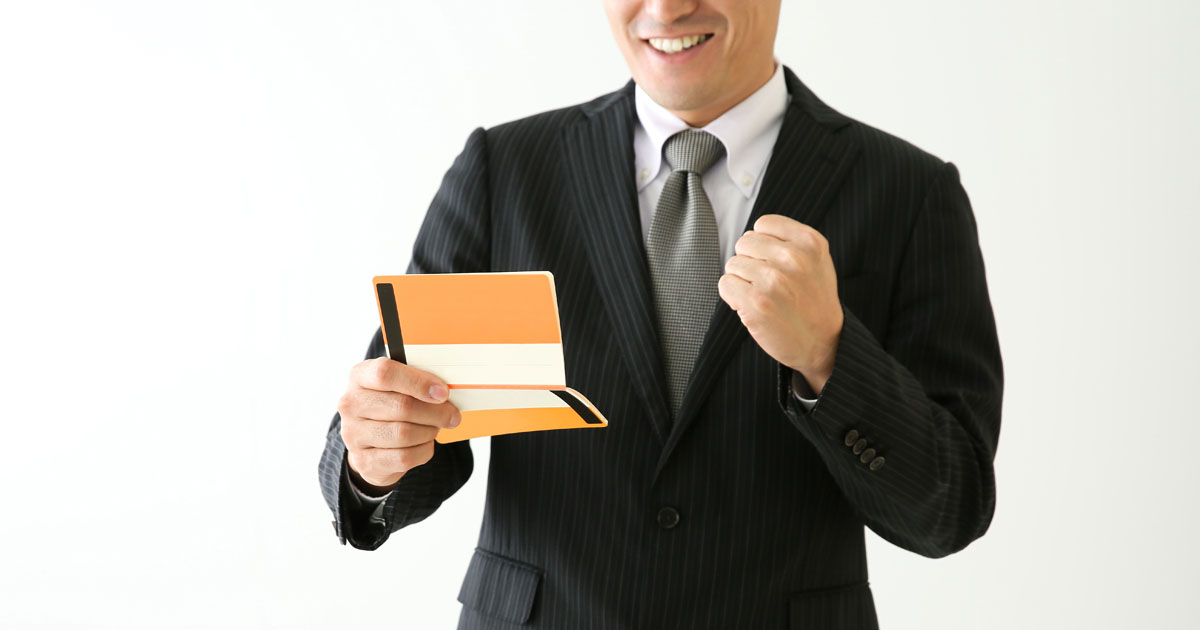
「米国積み立て投資を始めよう!」と思っても、たくさんある金融商品の中から何を選んでいいのかわからない人も多いだろう。そこで株式会社GCIアセット・マネジメント、エグゼクティブ・マネジャーの太田創さんは、金融商品の良し悪しを判断するための「8つの鉄則」を提唱する。積立投資を活用する上での“最高の1本”の見極め方とは――。全4回中の4回目。
※本稿は太田創著『毎月3万円で3000万円の「プライベート年金」をつくる米国つみたて投資』(かんき出版)の一部を抜粋・再編集したものです。
第1回:「2000万円問題」の大嘘…ゆとりある老後のために必要な「本当の金額」と「正しい計算方法」
第2回:「積み立て投資」だけで100億円の富を築いた日本人男性が、ドイツで学んだ「貯財術」の極意
第3回:それでも「米国株」を選ぶべき理由…「アメリカにだけ投資しておけば、それで十分」
鉄則1.無配分型を選ぶ
まずは、積み立て投資の効果を最大限にするために「無分配型」を選ぶこと。基本的に、長期的な資産形成を行う場合は、分配型よりも無分配型の方が有利です。分配金は、ファンドの運用資産の一部を売却してから支払われるものだからです。当然、組み入れ資産の売却に際しては、それに応じたコスト負担が生じます。また、収益の一部を分配してしまうと、その分だけ運用資産が目減りするため、運用効率が下がります。「複利効果」が得られなくなるのです。
当初の運用資産が100万円として、毎年5%の収益が得られるとしましょう。毎回、5%の収益を分配して30年間運用した場合、30年後の元本と利息の合計金額は250万円になります。一方、元本に加えて30年間運用すると、元利合計金額は432万1942円になります。この差は決して小さくありません。これが複利運用の効果です。しかも、無分配型は収益を分配せず内部に留保させたまま運用され、償還されるまで、運用収益に対して課税されないため、より効率的に運用できるというメリットも併せ持っています。
鉄則2.基準価額をあえてチェックしない
実際に投資信託による積み立て投資で成功している個人投資家の共通点は、「基準価額を頻繁にチェックしない」ことです。投資信託に組み入れられている株式などは、常に値段が上下していますし、米国株式になると為替レートの値動きも影響してくるため、基準価額はそれらの変動を受けて、日々、上下します。当然、値上がりすれば嬉しいでしょう。基準価額が値上がりしているということは、とりもなおさず自分が持っている投資信託に利益が生じていることになりますから。
それとは逆に、値下がりすればガッカリします。ただ、この一喜一憂が、長期の資産形成においては大敵になります。日々、基準価額は変動するものなのに、それに対していちいち喜んだり、がっかりしたりを繰り返していたら、まず自分の精神衛生上よくありません。また、それが余計な投資行動を誘発することにもなりかねないので、特に注意が必要です。
鉄則3.コストが安いネット証券を使う
口座を開く際、「どこの金融機関も一緒だろう」と思ってしまいがちなのですが、投資信託に限っていえば、それは正しくありません。投資信託は販売金融機関によって、独自の投資信託を扱っています。では、実際にはどこに口座を開くのがよいのかということですが、一番のお勧めはインターネット証券会社でしょう。その理由は、
- ①コストが安い
- ②品数が豊富
- ③こちらが望まない営業に付きまとわれずに済む
といったところでしょうか。コストに関しては、実店舗を持っている銀行、証券会社などとは比べ物にならないくらい安く買えます。それどころか、購入時手数料を、かなりの本数の投資信託に対して無料化しているところもあります。
鉄則4.非課税制度(iDeCoとNISA)をフル活用する
少しでも有利に増やすためには、非課税制度を積極的に活用することが鉄則です。それがiDeCoとNISAです。投資信託で運用した場合の利益はその20.315%が税金として源泉徴収されますが、iDeCoやNISAは、こうした運用益に対してかかってくる税金を、一定金額を上限にして非課税にしてくれます。
非課税になれば、その分だけ運用利回りの向上が期待できます。本当の理想を言えば、iDeCoとつみたてNISAの両方を満額で積み立てていくのが理想です。もちろん、その場合は「毎月3万円」ではなく、5万円近くになりますが、月々の積み立て金額が大きくなる分、最終的に受け取れる金額も大きくなります。
鉄則5.購入時手数料や運用管理費用が安いものを選ぶ
投資信託で運用するには、おもに2つのコストを負担する必要があります。「購入時手数料」と「運用管理費用」です。どちらもファンドによって異なりますが、たとえば最近は「ノーロード」といって、購入時手数料を取らない投資信託も増えています。同じスペックの投資信託なら、できるだけノーロードや運用管理費用の安いものを選んだ方が良いでしょう。
たとえば、運用管理費用が年率1%と年率2%の違いを数値で見てみましょう。両者の差は1%です。実は運用でパフォーマンスを1%引き上げるのは、非常に大変です。
仮に、運用成績が30年間で年平均5%のリターンがあったとすると、運用管理費用がない場合、元本は2.3倍になります。一方で、運用管理費用が年間1%かかる場合は1.9倍、2%かかる場合は1.6倍に減少します。倍数で見るとたいしたことありませんが、30年分の信託報酬は30%(1%×30年)と60%(2%×30年)になりますので、仮に元本が2500万円になっていたとすると、その間の運用管理費用は単純計算で400万円と750万円程度にもなります。
鉄則6.純資産総額の水準、資金流出入に注意する
「購入時手数料」が安く、「運用管理費用」が低いファンドも増えてきましたが、一方でこの手のローコストファンドには注意も必要です。運用管理費用の料率が低くても、数千億円単位の資金が集まるなら、運用にかかる経費を賄うことができますが、10億円に満たない資金しか集められない状態が続いたら、どうなるでしょうか。
たとえば集まった資金が10億円で、運用管理費用が0.3%でしたら、年間の収入は300万円にしかなりません。これを投資信託会社、受託銀行、販売金融機関の三者で分けるのですから、ビジネスとして考えた場合、採算に合わないと判断されます。そう判断された投資信託は、早晩、「繰り上げ償還」されます。つまり運用が中断されてしまうのです。
ですから、資金動向と、現時点の「純資産総額」の水準をチェックすることが大事です。純資産総額を見る際の1つの基準は、それが30億円を上回っているかどうかです。10億円、5億円というように、純資産総額の水準が非常に低い投資信託は、繰り上げ償還されるリスクが高まります。
次にチェックすべきは資金の流出入状況です。多くの投資信託は「追加型」といって、運用開始後、いつでも追加購入、解約ができる仕組みになっており、日々資金流入や資金流出が生じています。継続的に資金が流出している投資信託は、純資産総額の絶対水準にもよりますが、選ばない方が無難です。ましてや、純資産総額が30億円に満たないのに、資金流出が止まらないような投資信託は早晩、繰り上げ償還されるリスクが高いと判断するべきでしょう。
鉄則7.ダウかS&P500か、1つに絞る
S&P500指数に連動するインデックス型のファンドで長期積み立て投資をする、というところまで絞り込んだら、あとはパートナーとなる1本を選べばよいだけです。このとき、くれぐれも同じS&P500指数に連動する投資信託を複数買うことのないように。もしくはニューヨーク・ダウに連動するタイプとS&P500指数に連動する2本の投資信託に資金を分散するのも、全く意味がありません。
これは往々にして、投資信託の初心者がやってしまいがちなミスです。これは簡単に言うと、あれこれ買うと不要な手間や時間コストがかかるということです。つまり〝トータルリターン〟が下がります。同じ株価インデックス、あるいはニューヨーク・ダウとS&P500指数では、値動きの方向性がほぼ同じなので、分散投資効果が得られたことにはならないのです。
つまり米国株式に投資するのであれば、ニューヨーク・ダウ連動型か、S&P500指数連動型の「いずれか1本」を選べば十分ということになります。
鉄則8.3000万円積み立てた「後」を計画する
積み立て投資はその入口、つまり積み立て投資を始める「ベストなタイミング」は、ありません。それこそ、思い立ったが吉日ではありませんが、積み立て投資を始めてみようと思ったら、とにかくすぐ始めることが肝心です。でも出口、つまりどのタイミングで積み立てをやめるかについては、少し計画性を持たせた方がよいでしょう。
選択肢のひとつは定年退職を積み立て投資のゴールにすること。それまでに3000万円の資産をつくっておき、公的年金が受け取れるようになったら、年金に加え3000万円の資産を徐々に取り崩して、月々の生活資金をより豊かなものにしていきます。
ここで考えなければならないのは、ゴールに達した時点で、積み立ててきた投資信託を全額換金するべきかどうかです。全額解約はお勧めできません。大事なことは、運用しながら取り崩していくことです。なぜなら、それによって「お金の持ち」が違ってくるからです。
仮に、3000万円の原資から毎月15万円ずつ引き出しながら、残額を年平均5%で運用し続けたとしたら、いつまで持つでしょうか。答えは34年7カ月です。ということは、65歳からの34年7カ月ですから、99歳と7カ月くらいまでは、3000万円が底を尽かずに済みます。そうそう老後を心配する必要はないでしょう。