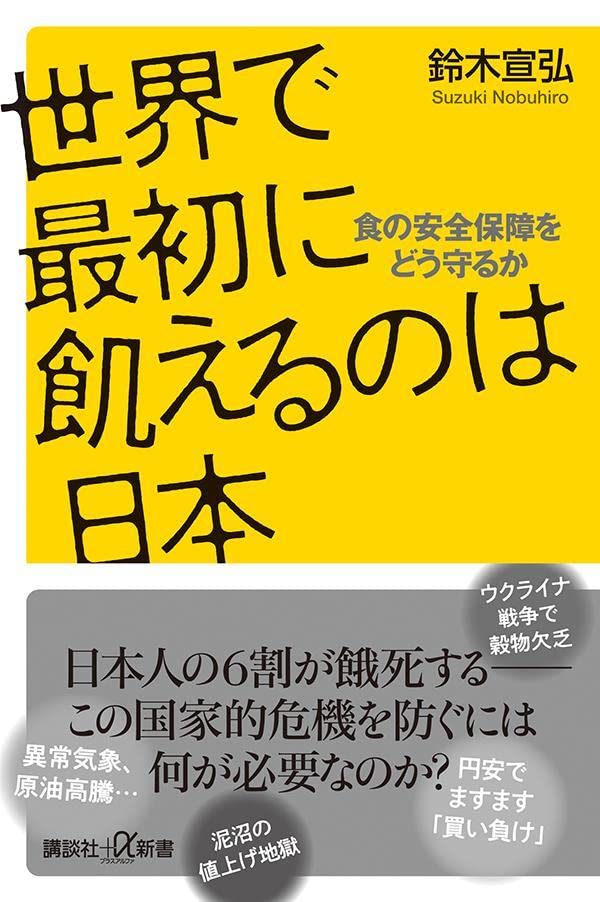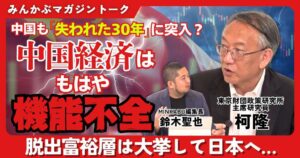えっ…「代替農薬」「ゲノム編集」を使った農業は「有機栽培」扱いなの!? 巨大ITテックに飲み込まれる日本農業

大手IT企業が農業分野への進出攻勢を強めている。東京大学大学院農学生命科学研究科教授で食料安全保障推進財団理事長の鈴木宣弘氏は、「農業のデジタル化に反対ではない」としながらも、既存の農家が追い出されかねない現状に警鐘を鳴らす。本来の農業のあるべき姿と、その農業を支えるための国民のあり方を問う――。全4回中の4回目。
※本稿は鈴木宣弘著『世界で最初に飢えるのは日本』(講談社)から抜粋・編集したものです
第1回:国民が餓死することに…衝撃の真実!岸田外相時代に結んだ日本農業”アメリカ奴隷契約”の中身「これは人災だ!」
第2回:もうすぐ三食イモに、ゴルフ場をイモ畑に…国民は知らない「世界で最初に餓えるのは日本」という真実
第3回:国民絶望「なぜ日本人はコオロギを食べようとしているのか」…牛乳を捨て、牛を殺処分しているのに
「代替農薬」「ゲノム編集」を活用した農業が「有機栽培」と呼ばれる未来
いま、世界各国では食料戦略の転換が進んでいる。欧州では、農薬使用量の半減や、有機農業面積を25パーセントに拡大するといった目標を掲げる「Farm to Fork」(農場から食卓まで)戦略が策定されている。
またアメリカは、カーボンフットプリント(生産・流通・消費工程におけるCO2排出量)の大幅削減などを目標とする「農業イノベーションアジェンダ」を2020年に公表している。
一方、こうした世界の潮流に取り残されつつある日本が掲げるのが「みどりの食料システム戦略」である。
2050年までに、農林水産業のゼロエミッション化の実現、化学農薬使用量の低減、有機農業面積の拡大、地産地消型エネルギーシステム構築に向けての規制見直しの検討のほか、「政策手法のグリーン化(一定レベルの環境に優しい農法をしていないと農業補助金を受給できない=クロス・コンプライアンス)」も目指すとしている。
目標数値の提示は無理かと思われたが、なんと、2050年までに稲作を主体に有機栽培面積を25パーセント(100万ヘクタール)に拡大、化学農薬5割減、化学肥料3割減を打ち出している。これらは、欧州が掲げる目標とほぼ同じ水準だ。
数値目標は評価できる一方、本当にたしかな有機農業を推進できるかという点には懸念もある。世界で農薬削減の流れが起きている中、「代替農薬」として、害虫の遺伝子の働きを止めてしまうRNA農薬が視野に入れられている。
このRNA農薬は、化学農薬に代わる次世代農薬として、すでにバイオ企業によって開発が進められている。化学農薬の代わりに、このRNA農薬を使って、「有機栽培」を名乗ることが認められたら、本末転倒である。
小売り大手が有機農産物を囲い込むことも、農産物の買い叩きを余計に助長してしまうだろう。有機農業から得られる利益が、農家ではなく、企業に還元されるのではないかという懸念が拭えない。
また、ゲノム編集作物について、大々的に推進する方向を打ち出している点も懸念される。ゲノム編集作物は、予期せぬ遺伝子損傷が起こるとされ、世界的に懸念が高まっているからだ。ゲノム編集作物であっても、いずれは「有機栽培」を認めるつもりなのだろうか。
また、イノベーション、AI(人工知能)、スマート農業技術などの用語が並んでいる点も違和感を覚える。こうした技術の活用に反対ではないが、いま日本の農業が抱える課題が、スマート化だけで解決できるとは思えない。「高齢化、人手不足はAIで解決する」という方向性は、「農家が消え、コミュニティが崩壊したあと、AIを駆使した企業が農業を独占する」という姿にも見える。
バイオ企業などは、いわゆるスマート農業技術も含め、IT大手とも組んで、農業生産工程全体をトータルに包含したビジネスモデルを展開しつつあるからだ。
政府としては、むしろ「多様な農家が共存しつつ、コミュニティを持続する」方向性を打ち出すべきではなかったか。中小経営や「半農半X」を含む、多様な経営体が地域農業とコミュニティを支えることを再確認した、2020年の「新たな食料・農業・農村基本計画」とも相反するように思われる。
“GAFAの農業参入”で既存の農家がいなくなる
こうした食料戦略が、企業利益の追求に利用されることは避けなければならない。世界の食料企業は、IT分野への進出を強めている。バイエル社(旧モンサント社)は、化学肥料市場から、遺伝子組み換え作物へ視点を変えて急成長。2013年には新たな戦略の一環として、農業プラットフォームサービスのClimate社を買収している。
バイエル社の狙いは、食料供給におけるソリューション提供企業への変身にある。買収したClimate社を通じ、農業機器の製造・販売大手のAGCOや、農機具メーカーのJohn Deereのオペレーションセンターとデータの相互接続をするといった取り組みが行われている。
これによって、農地の肥沃度管理や、区画ごとの収量分析、地域の気象データ確認などの作業を、一つのプラットフォーム上で行う、デジタル農業技術ソリューションを提供している。
そうした中、農業生産者はClimateの利用が必須になり、ますますバイエル社への依存を強めることが懸念される。ここに、GAFA(Google、Apple、Facebook〈現Meta〉、Amazon)などのIT大手企業も加わることで、農業のより一層の省人化が進めば、既存の農家が追い出されかねない。
ドローンやセンサーで管理・制御されるデジタル農業で、種から消費までの儲けを最大化するビジネスモデルが構築され、それに巨大投資家が投資する未来も見えてくる。
現に、2022年9月に開催された国連食料システムサミットは、ビル・ゲイツ氏らの主導による、デジタル農業推進のキックオフに位置づけられたとも言われている。実際、ビル・ゲイツ氏はアメリカ最大の農場所有者になっており、マクドナルドの食材もビル・ゲイツ氏の農場が供給しているというニュースも報じられている。
「卵が高いのは当たり前」と話すスイスの小学生
ビル・ゲイツ氏がおそらく考えているであろう、データ化とAI・ロボット・ドローンの導入によるデジタル農業は、既存の農家にとっては脅威になる。だが、そうしたデジタル農業が「今だけ、カネだけ、自分だけ」の目先の自己利益を追求すると、本当に食料危機に備える「食の安全保障」や、地域コミュニティの維持、環境への配慮がおろそかにされる懸念がある。
カナダの牛乳は1リットルあたり300円と、日本より大幅に高い。だが、消費者はそれに不満を持っていない。筆者の研究室の学生が行ったアンケート調査では、カナダの消費者から「米国産の遺伝子組み換え成長ホルモン入り牛乳は不安だから、カナダ産を支えたい」という趣旨の回答が寄せられた。
スイスの卵は、国産の場合1個あたり60~80円もする。輸入品の何倍もの価格だが、それでも国産の卵のほうがよく売れていた(筆者も見てきた)。小学生くらいの女の子が卵を買っていたので、質問してみると、その子は「これを買うことで生産者の皆さんの生活も支えられ、そのおかげで私たちの生活も成り立つのだから、高くても当たり前でしょう」と、いとも簡単に答えたという(元NHKの倉石久寿氏による)。
農家・メーカー・小売りのそれぞれが十分な利益を得た上で、消費者もハッピーなら、牛乳1リットルあたり300円、卵1個80円でもまったく問題はない。むしろ、これこそ真の意味で持続的なシステムではないか。関係者全員が幸せであり、日本の近江商人の格言「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」が実現されているからだ。
キーワードは、ナチュラル、オーガニック、アニマル・ウェルフェア(動物福祉)、バイオダイバーシティ(生物多様性)、そして美しい景観である。これらに配慮して生産されていれば、ホンモノであり、安全で、かつ美味しい。これらのキーワードはつながっている。値段が高いのではなく、そこに注入された価値を皆で支えていこうという意志が込められている。
イタリアの水田の話も、非常に示唆的だ。水田にはオタマジャクシなどさまざまな生き物が棲み、生物多様性が保たれている。また、ダムの代わりに貯水する洪水防止機能、水を濾過してくれる機能など、さまざまな機能を果たしている。
水田のこうした機能に、イタリア国民は常にお世話になっているが、それはコメの値段に反映されていない。もし、十分反映されていないなら、イタリア国民は水田に「ただ乗り」しているのである。
その場合、「農業にただ乗りしてはいけない。お金を集めて、農業にもっと払おうじゃないか」という感覚を持つのが、世界の常識である。実際に、イタリアではこういった考えに基づき、税金を使って農家への直接支払いを行っている。
筆者らが2008年に訪問したスイスの農家では、豚の食事場所と寝床を区分し、自由に外に出て行けるように飼うと230万円、草刈りをし、木を切り、雑木林化を防ぐことで、草地の生物種を20種類から70種類に増加させることができるので、それに対して170万円、というようなかたちで財政からの直接支払いが行われていた。
農業の果たす多面的機能の項目ごとに、支払われる直接支払額が具体的に決められているから、消費者の納得を得られやすく、直接支払いが「バラマキ」と言われることもない。農家もそれを認識し、誇りをもって生産に臨んでいる。こうしたシステムが日本にも必要なのではないだろうか。