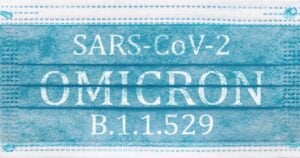第2回 熱海土石流災害[その2]「万が一」の被害、住居の再建・修理に必要な自己資金を把握せよ!

本連載は、ニュースで報道される事故・災害などをファイナンシャルプランナーが調査して、その被害額、行政支援、資産を守るための方法などの情報を、皆さんにお知らせしています。
今回は「熱海土石流災害」の2回目。住居の再建・修理費用について「支援金はいくらか」「自己資金はどれくらい必要か」などについてお話ししたいと思います。
目次
警戒区域の設定および支援の強化
先月16日、熱海市は伊豆山地区で発生した土石流災害に対して災害対策基本法第63条の適用を決定しました。
この条文の適用により、土石流の被災地には福島原発事故と同様の警戒区域が設定され、無許可で警戒区域に立ち入った場合、罰則が適用されるようになりました。
したがって土石流災害の被災地は、現在、住居の再建・補修ができない状況(警戒区域外で住居を新規に購入したり、新たに賃借したりすることは可能)ですが、本記事では、同様の災害が起きたときの参考とするため、同じ土地に再建する、もしくは現在の住居を修理することを前提として再建・修理費用を計算してみました。
なお災害対策基本法第63条の適用前は、住居が全壊~半壊でなければ仮設住宅に入居できなかったのですが、同条文の適用後は警戒区域内の住民は自宅に被害がなくても入居可能となりました。また同条文の適用により罹災証明書がなくても公営住宅に入居できたり、新たに生活必需品が給付されたりするなど、その後の行政による被災者支援がさらに強化されています。
住居を再建するときの自己負担は?
それでは被災者生活再建支援法が適用された場合の住居の再建費用、支援金の給付額および必要な自己資金について計算してみましょう。
なお以下の計算の支援金額は2人以上世帯の場合です。単身世帯の場合、被災者生活再建支援法の支援金は3/4相当に減額されますのでご注意ください。
住居が全壊し、再建する場合
| (A) 基礎支援金 100万円 + 加算支援金(建設・購入)200万円 = 支援金 300万円 |
| (B) 再建費用 2500万円 - 給付額 300万円 = 自己負担 2200万円 |
※まず(A)被災者生活再建支援法によって受け取ることができる金額(支援金)を計算し、次に(B)再建費用から給付額を差し引いた金額(自己負担)を求めた。
※(B)個々の住宅の再建費用については調査が難しいため、東日本大震災で全壊被害に遭った住宅の再建費用の平均(約2500万円)で計算した。
住居が大規模半壊し、再建する場合
| (C) 基礎支援金 50万円 + 加算支援金(建設・購入)200万円 = 支援金 250万円 |
| (D) 再建費用 2500万円 - 給付額 250万円 = 自己負担 2250万円 |
※ 1. と同様に支援金と自己負担を求めた。
住居が中規模半壊し、再建する場合
| (E) 基礎支援金 なし + 加算支援金(建設・購入)100万円 = 支援金 100万円 |
| (F) 再建費用 2500万円 - 給付額 100万円 = 自己負担 2400万円 |
※ 1. と同様に支援金と自己負担を求めた。
住居が半壊、準半壊または一部損壊し、再建する場合
| (G) 基礎支援金 なし + 加算支援金(建設・購入)なし = 支援金 なし |
| (H) 再建費用 2500万円 - 給付額なし = 自己負担 2500万円 |
※(G)被災者生活再建支援法による給付金はないので、(H)再建費用は全て自己負担となる。
住居を補修するときの自己負担は?
被災者生活再建支援法および災害救助法が適用された場合、住居を補修する被災者は、被災者生活再建支援金と住宅応急修理に基づく給付金の2種類の給付を受けることができます。
なお罹災証明書の認定基準の中に「住家の損壊……した部分の床面積の延べ床面積に占める損壊割合が70%以上(全壊)」または「50%以上70%未満(大規模半壊)」というものがありますが、もし自分が暮らしている住居がこれだけ損壊したら、被災した住居を取り壊し、再築もしくは他の住宅を購入するのが一般的だと思います。
しかし制度上は、全壊および大規模半壊も住宅応急修理の給付の対象となっているので、本記事では制度どおり補修できるものとして計算します。
また以下の支援金額は2人以上世帯の場合です。単身世帯の場合、被災者生活再建支援法の支援金はが、単身世帯の場合は3/4相当に減額されますますのでご注意ください。
住居が全壊し、補修する場合
| (I) 基礎支援金100万円 + 加算支援金(補修)100万円 (J) 住宅応急修理 1世帯あたり59万5000円 = 支援金額 259万5000円 |
| (K) 補修費用1250万円 − 給付額259万5000円 = 自己負担 990万5000円 |
※全壊と認定された住居は通常は解体・再建されているが、住宅応急修理制度では応急修理を実施することにより居住が可能である場合は支援の対象になる。
※(J)住宅応急修理の給付額は大規模半壊と同額で計算した。(K)補修費用については、実際の金額を調査するのが困難なので、仮に再建費用の2分の1(1250万円)とした。
住居が大規模半壊し、補修する場合
| (L) 基礎支援金50万円 + 加算支援金(補修)100万円 (M)住宅応急修理 1世帯につき59万5000円 = 支援金 209万5000円 |
| (N) 補修費用1250万円 − 給付額209万5000円 = 自己負担 1040万5000円 |
※(N)補修費用は、全壊と同様とした。
住居が中規模半壊し、補修する場合
| (O) 基礎支援金なし + 加算支援金(補修)50万円 (P) 住宅応急修理費用 1世帯当たり59万5000円 = 支援金 109万5000円 |
| (Q) 補修費用833万円 - 支援金109万5000円 = 自己負担 723万5000円 |
※(Q)補修費用は、仮に再建費用の3分の1(833万円)とした。
住居が半壊し、補修する場合
| (R) 基礎支援金なし + 加算支援金(補修)なし (S) 住宅応急修理費用 1世帯当たり59万5000円 = 支援金 59万5000円 |
| (T) 補修費用 625万円 - 支援金 59万5000円 = 自己負担 565万5000円 |
※(T)補修費用は、仮に再建費用の4分の1(625万円)とした。
住居が準半壊し、補修する場合
| (U) 基礎支援金なし + 加算支援金(補修)なし (V) 住宅応急修理費用 1世帯当たり30万円 = 支援金 30万円 |
| (W) 補修費用 312万5000円 - 支援金 30万円 = 自己負担 282万5000円 |
※(W)補修費用は、仮に再建費用の8分の1(312万5000円)とした。
住居が一部損壊し、補修する場合
| (X) 基礎支援金なし + 加算支援金(補修)なし (Y) 住宅応急修理費用なし = 支援金なし |
| (Z) 補修費用 156万2000円 - 支援金なし = 自己負担 156万2000円 |
※(Z)補修費用は、仮に再建費用の16分の1(156万2000円)とした。
この場合、被災者生活再建支援金および災害救助法における応急修理費用は給付されず、全額を自己負担することになります。