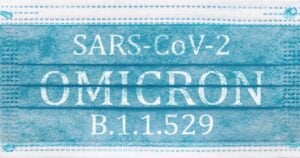第5回 通勤災害[その2]被害発生、労災保険の給付を把握せよ!

※写真はイメージです。
本連載は、ニュースで報道される事故・災害などをファイナンシャルプランナーが調査して、その被害額、行政支援、生活や資産を守るための対策などをお知らせしています。
今回は「通勤災害」の第2回です。
前回は、通勤災害の概要と、労働者災害補償保険制度(以下、労災保険)で補償される場合と補償されない場合(通勤における移動の範囲および逸脱・中断)についてご説明しました。
今回は、通勤災害によって発生した損害を補償してくれる労災保険の給付についてお話ししたいと思います。
目次
通勤災害を補償する労災保険
労働者災害補償保険制度すなわち労災保険は、労働者の業務または通勤によって発生したケガや病気に対して保険給付が行われる補償制度です。
労災保険は、原則として1人でも労働者を雇用していたら業種を問わず全ての事業所に適用されます。
労災の保険料は労働者ではなく事業主が負担します。また、この場合の労働者には正社員だけではなくアルバイトやパートタイマーも含まれます。
通勤災害の具体例
通勤災害はその性質上、朝と夕方の事例が多く、冬場(12~2月)は路面凍結による事故が数多く発生しています。
出勤時の事例
階段からの転倒事故
就業場所の最寄り駅の構内で階段を下りようとしたところ、その階段は雨が降った後で濡れており、また落ち葉も落ちていたため、踏み外して滑り落ちてしまいました。病院で受診したところ、足首が捻挫していることが分かりました。
転倒による頭部外傷事故
就業場所にたどり着く直前、就業先の敷地内で転倒して頭部を強く打ちつけてしまい、なんとか就業場所までたどり着いて社員通用口でうずくまっているところを他の従業員が発見しました。救急車で搬送して病院で検査した結果、右頭部脳内の外傷性くも膜下出血でした。
退勤時の事例
転倒事故
退勤時間になったので帰宅準備のためロッカールームに向かいました。その途中、手洗い場とエントランス空間を仕切っている引き戸を開けてエントランス空間に出ようとしたところ、引き戸の下にある5ミリほどの高さのレールに右足のつま先を引っ掛け、前のめりに転倒しました。事故直後は痛みをさほど感じず、大丈夫だと思ってそのまま帰宅したそうですが、しばらくしてコンクリートの床にぶつけた顔面と左手首に腫れと痛みが出たため、病院に行きました。
凍結路面の転倒事故
新聞の朝刊の配達を終了し、駐車していた自家用車に乗り込もうとしたところ、凍結した路面で足を滑らせて左足首をひねってしまいました。帰宅後、徐々に左足首全体が腫れてきたので病院を受診したところ、骨折していることが分かりました。
このように思わぬところに通勤災害が潜んでいるため、通勤や退勤時は不注意がないように気を付ける必要があります。
通勤災害で受けられる5種類の給付
前章のような通勤災害の被災者は、労災保険から以下の給付を受けられます。
- 療養給付※
- 休業給付※
- 遺族給付※
- 障害給付※
- 介護給付※
※労災保険による給付は、労災の種類によって呼称が異なる。
療養給付 …… 業務災害では「療養補償給付」、複数業務要因災害では「複数事業労働者療養給付」と呼んでいる。
休業給付 …… 業務災害では「休業補償給付」、複数業務要因災害では「複数事業労働者休業給付」と呼んでいる。
遺族給付 …… 業務災害では「遺族補償給付」、複数業務要因災害では「複数事業労働者遺族給付」と呼んでいる。
障害給付 …… 業務災害では「障害補償給付」、複数業務要因災害では「複数事業労働者障害給付」と呼んでいる。
介護給付 …… 業務災害では「介護補償給付」、複数業務要因災害では「複数事業労働者介護給付」と呼んでいる。
それではこれらの給付について細かく見ていきましょう。
療養給付
通勤が原因で負傷したり病気にかかったりして療養を必要とするときに支給されます。
給付には、療養のために通常必要とされる費用(治療費、薬剤費、入院費、移送費、通院費など)が含まれ、原則として病気やケガが治癒するまで支給されます。
この給付の内容は2種類あります。
| 1.現物給付 | 指定医療機関等(労災病院や労災保険指定医療機関・薬局)で、無料で治療や薬剤の支給を受けられます。 |
| 2.現金給付 | 近くに指定医療機関等がないなどの理由により指定医療機関等以外で治療を受けたり、薬剤の支給を受けたりした場合、(健康保険に適用されないため)いったん費用の全額を負担し、労働基準監督署にかかった費用を請求します。 |
休業給付
通勤でケガや病気をし、その療養のため働くことができなくなり賃金を受け取っていないときに支給されます。
休業給付は災害発生後4日目から給付が始まります。1~3日は待機期間といって給付がありません※。
※業務災害では、待機期間の間に労働基準法第26条に定める休業補償(1日につき平均賃金の60%)が支払われる場合がある。
休業給付の給付額は表をご覧ください※。
※(表の)給付基礎日額とは、労災が発生した日の直前3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った1日当たりの賃金額のこと。労災の給付は、この金額を基に支給額が決定される。なお複数事業労働者(複数の会社の職場で働いている人)の給付基礎日額は、原則として各事業の給付基礎日額を合算した額になる。