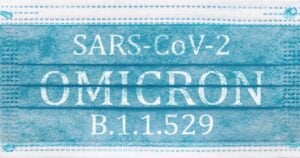第6回 通勤災害[その3]労災認定の有無による自己負担額の違いを把握せよ!
![第6回 通勤災害[その3]労災認定の有無による自己負担額の違いを把握せよ!](https://mag.minkabu.jp/wp-content/uploads/2021/11/fpnews-commute-disaster-part3-1-scaled.jpeg)
※写真はイメージです。
本連載では、ニュースで報道される事故・災害などをファイナンシャルプランナーが調査して、その被害額、行政による救済、資産を守る方法などをお知らせしています。
前回は労働者災害補償保険制度の給付内容について詳しくご説明しました。
今回は、労働災害(以下、労災)認定の有無によって医療費の支払いがどう変わるか、および通勤災害をカバーする民間保険についてお話ししたいと思います。
目次
万が一、通勤時に被災してしまったら…
10月31日(日)、京王線車内で刺傷事件が発生しました。報道によると、犯人は小田急線刺傷事件や映画「Joker(ジョーカー)」を模倣したと話したそうです。
この事件は日曜日に発生したため、通勤災害に該当する被害者は少なかったと考えられますが、もしラッシュ時に犯行がなされていたらどうなっていたでしょうか。おそらく多数の通勤災害が発生したと思います。
こうした通勤災害に巻き込まれ、負傷したり病気になったりした場合、労災保険から補償を受けるためには、まず労働基準監督署に申請書を提出して「労災認定」されなければいけません。
労災認定された場合
通勤災害の被害者が労災認定されるためには、被害者が「通勤に際しての移動」中であったと認められ、さらに「移動経路の逸脱・中断」がないことが必要です(第4回参照)。
通勤災害が労災認定されると、基本的には治療や療養の費用がかかりません※。
※労災病院・労災保険指定医療機関で受診した場合、および労災保険指定薬局で薬剤を処方してもらった場合は医療費を支払う必要がない(現物給付、第5回参照)。それ以外の病院、医療機関、薬局を利用した場合は一旦10割を支払う必要があり、後日、労働基準監督署へ請求書を提出すると全額の補償(現金給付)が受けられる(第5回参照)。なお看護、通院などにかかった費用(市販薬の購入代金、通院の際の交通費など)も補償されるため、これらの領収書は捨てずに保管しておく。
労災認定されなかった場合
被災したとき「通勤に際しての移動」中ではなかったり、「移動経路の逸脱・中断」があったりすると、たとえ通勤途中であっても労災とは認められません(第4回参照)。
また労災は、被災者に原因がある場合も認定される可能性がありますが、自分に重大な落ち度があるような場合は認められません。
例えば、通勤途中によそ見をして転倒し骨折してしまったら労災認定される可能性が十分ありますが、自動車通勤の途中で酒気帯び運転による事故を起こしたら労災認定が認められないか、認められたとしても給付が制限されてしまうでしょう。
労災認定されなかった場合にやるべきことは以下の3点です。
- 健康保険を利用して医療機関で診療を受ける
- 医療費が高額になった場合は、高額療養費制度を利用する
- 民間の保険会社に保険金の支払いを請求する
また、労働基準監督署が労災認定をしなかったことについて労働局に処分の不服申し立て(審査請求)ができ、審査の結果、被災者の主張が認められれば労災が認められます。
健康保険を利用する
労災認定されなかった場合、通常のケガや病気と同じように健康保険を使って診療を受けることになります。
1. 入院した場合の自己負担額
健康保険を使って治療すると、原則3割の自己負担が発生します。
ケガ・病気による入院時の自己負担額(平均値)※は下表のとおりで、労災認定されなかった場合は平均37万円弱※の出費があると考えられます。ただし、次に述べる高額療養費制度の給付を受けることができます。
※ 生命保険文化センター「令和元年度生活保障に関する調査」より引用。集計ベースには日常生活におけるケガ・病気の数字も含まれる。
.png)
2. 高額療養費制度を利用する