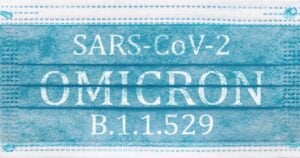第13回 高齢ドライバー[その3] 深刻な事故発生、補償の優れた自動車保険を「最後の砦」とせよ!

前回は、高齢ドライバーが起こしやすい事故とそれを防ぐための対策についてご説明しました。
今回は、高齢ドライバーの交通事故に備える自動車保険(任意保険)について考えてみます。
目次
任意保険の年齢条件とは
自動車保険(任意保険)では、運転者の年齢に合わせて年齢条件を設定すると、保険料を割り引いてもらえます(下図)。
年齢条件はまず「運転者の年齢範囲」の区分があり、これは自分で自由に選んで決めることができます。
そして運転者の年齢範囲で「26歳以上」を選択した場合のみ、2つめの年齢条件「記名被保険者の年齢層」の自分が該当する区分で契約を結ぶことになります。

「運転者の年齢範囲」による区分
運転者の年齢範囲とは、車を実際に運転者する者の年齢を基準に設けられた年齢条件です。普通は「全年齢補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」の3種類※の区分があります(下図)が、中には「30歳以上補償」「35歳以上補償」といった区分を設けている保険会社もあります。

これらの区分は補償対象者の範囲を年齢によって限定するもので、範囲を狭く(年齢を高く)設定すると保険料を大幅に安くすることができます※。
※26歳以上補償の保険料は、全年齢補償の約3分の1です。
ただし適用されるのは同居の家族等※だけ。別居している親子や友人などは適用されません。
したがって「同居していない19歳の孫が車を貸して欲しいと言ってきた」「ドライブ中に疲れたので、友人の19歳の子に運転を代わってもらう」という場合などは、全年齢補償でなくても(21~35歳以上の区分でも)補償を受けられます。
※「同居の家族等」とは以下の人を言います。1. 記名被保険者、2. 記名被保険者の配偶者、3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、4. 1 ~ 3に該当する人の業務(家事を除く)に従事中の使用人。保険会社によって異なる場合もあるため必ずご確認ください。
「記名被保険者の年齢層」による区分
26歳以上の年齢条件は、記名被保険者(その車を主に運転する人)の年齢層によってさらに6つの区分が設けられています(下図)。

この区分は、高齢ドライバーは事故を起こすリスクが高いという状況を反映して設けられているため、保険料は「70歳以上」が最も高くなっています※。
※対人賠償責任保険の場合、30歳未満と70歳以上の差は約1.34倍です(損害保険料率算出機構「自動車保険の概況2020年度版」)。