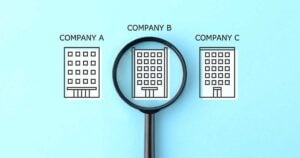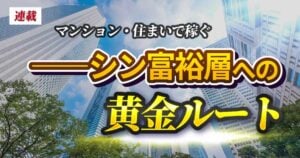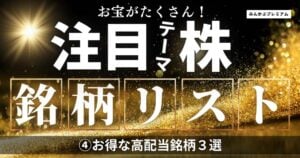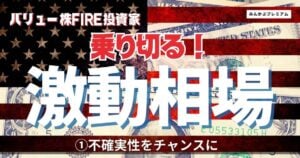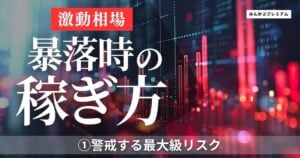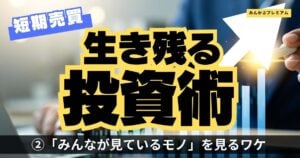すみません、複利ってなんですか? 知らない日本人はこれから「野垂れ死にます」

「金融の知識を持たない日本人は、将来野垂れ死んでしまう」——。こう警鐘を鳴らすのは、自身のTwitterやnoteで投資の情報を発信しているレイチェルさんだ。これからの社会を生き抜くための手段として投資を推奨しているレイチェルさんが、投資を始める上で押さえておくべき三つの基本について語る――。 全4回中の1回目。
※本稿はレイチェル著『月3万円で3408万円の超安心資産をつくる! 毎月“5分”のシン・米国株投資術』(KADOKAWA)から抜粋・再編集したものです。
第2回:やっぱり「S&P500」か、それとも「オルカン」か…米株投資のレイチェルが出した答えとは
第3回:投資家レイチェル「金持ちになりたいなら『投機は必要』」…”嫌われ者”レバレッジの正しい使い方
第4回:日経電子版で朝5時に配信される”とある記事”…米株投資家なら「絶対読め」
国民全員に必要な金融リテラシー
2022年4月より、高校である授業が必修となりました。「金融経済」と「資産形成」です。なぜ、高校で金融リテラシーの授業が必修となったのか? それは、国としてその知識が高校生に必要だと認めたからにほかなりません。言い換えれば、日本国民全員にとって金融の知識が必要ということです。高校生が必要なぐらいですからね。
では、なぜ金融の知識が必要なのでしょうか? 金融の知識がないとどうなってしまうのでしょうか? はっきりと言います。日本の現状では、金融の知識がないと、野垂れ死んでしまいます。野垂れ死ぬという表現は少し過激ですが、実際に金融リテラシーがなくて困っている人が、大勢いるのが実情。ですから、政府としても、学校の授業に金融の知識を組み込むことによって、野垂れ死ぬ人、もとい、お金で困る人を一人でも減らそうとしているのです。
しかし、妙だと思いませんか? 昔は必要なかった金融リテラシーの知識が、今は政府が学校教育に取り入れるぐらい必要になっている。なぜ、昔はいらなかったものが、今では必要になったのか? その理由は、環境が変わったからです。世の中は激変しています。
たとえばiPhoneをはじめとするスマホが、日本で普及しだしたのは、だいたい2010年ごろから。私たちが当たり前のように使っているLINEの登場は2011年で、広く使われるようになったのは2013年ごろからです。以前はなかった産業なども生まれ、それまでは存在しなかった職業も次々と生まれました。ユーチューバーがいい例ですね。
たった10年ちょっとの間に、私たちの生活環境は大きく変化し、それに合わせて必要な知識もまた変わったのです。世の中の変化は速く、激しい! そんな中、お金を取り巻く環境も大きく変わっていきました。それにともない、金融リテラシーという知識が必要になっていったというわけです。
投資に欠かせない3つのキーワード
働いて稼ぐだけではお金が足りず、生活が苦しくなってしまう世の中になりました。そのような現況で、労働以外でお金を得る手法として私が推奨しているのが、「米国株投資」です。ただし、投資を始めていくうえで、絶対に欠かせないキーワードが3つあります。これらを知っておくだけで、投資で損をする確率を減らせるでしょう。